皆さんは”include”をどう訳すでしょうか。やはり「含む」でしょうか。
しかし文脈によっては、「含む」と訳出すると不自然な場面があると思います。
私が遭遇した”include”=「含む」の不自然な場面を例に、見ていきたいと思います。
まずは、”include”の意味についておさらいしておきましょう。
ジーニアス英和辞典第4版によると、”include”には大きく以下2つの意味があります。
- 含む、包括する
- 算入する、勘定に入れる、部類に入れる、同封する
多くの場合、1の意味で使われることが多いかと思います。
ただ、文脈に応じて「含む」を言い換えなければ、不自然な日本語になってしまいます。
例として、以下の英文を見てみましょう。これは、とある企業のwebページの一文です。
原文:For instance, a warehouse might develop a standard operating procedure for receiving new stock, which could include steps for quality checks, labeling, and storage.
Google訳:たとえば、倉庫では、新しい在庫を受け取るための標準的な操作手順を開発する場合があります。これには、品質チェック、ラベル付け、保管の手順が含まれる場合があります。
上記のGoogle翻訳のように、直訳すると「手順が含まれる」となります。
この訳文、皆さんはどう感じるでしょうか。特に違和感はないでしょうか。私的には、「含まれる」の部分がとても気になります(普段使う日本語で、「含まれます」という表現を使わないからですかね…)。
「含まれます」の表現を避けつつ、私は以下のように翻訳してみました。
じょにー訳:たとえば倉庫の場合、新しい在庫商品を受け取る際の標準作業手順を作成し、その中に品質チェック、ラベリング、入庫の手順を組み込むとよいでしょう。
先行する節に「手順を作成」とあるので、”include”は「その手順に含める」=「その手順に組み込む」としました。
また、この文章は「プロセスを標準化して一貫性を保つ」という文脈の中で出現するため、「~するとよいでしょう」という言い回しにしました。
いかがでしたでしょうか。
“include”は「含む」と訳出することが多いですが、状況に応じた表現に変える必要がありそうですね。
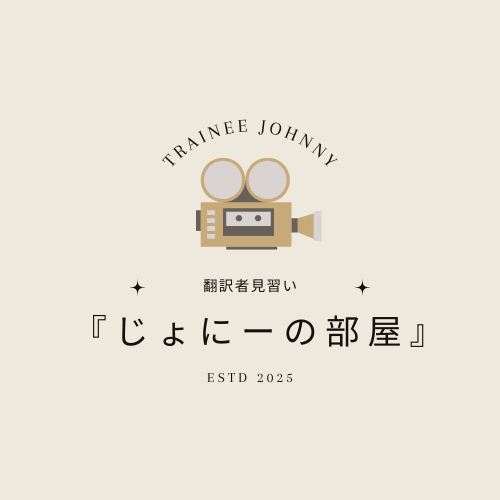


コメント