日本語表現力が求められる理由
映像翻訳では、視聴者の多くが日本語しか理解できません。また、本来視聴者は字幕を読むこと自体を望んでいません(そもそも原語で理解できるに越したことはないのですから…)。そのため字幕の内容は、一回読んだだけで直感的に理解できる必要があります。
近年はChatGPTを代表とするAI翻訳の登場により、機械でも一定レベルの訳文が作成可能になりました。「今や機械でさえ誤訳のない訳文を作れる時代」です。それでもプロの翻訳者が必要とされるのは、原文の細かな背景や行間にあるニュアンスまで忠実に読み手へ届ける、巧みな日本語表現力を持っているからです。つまり、人間の翻訳には機械にはない読みやすさと伝わりやすさが求められており、その鍵となるのが日本語の表現力なのです。
さらにプロの翻訳者として仕事を得るには、「選ばれるための日本語」を使いこなすことが重要です。英語力だけでなく、日本語で魅せる力がなければ、クライアントや視聴者に選ばれ続けることはできません。実際、多くの翻訳者志望者は日頃から日本語表現を体系的に学んでいないことが多いため、「なんとなく」書いてしまいがちです。その結果、自身の日本語の弱点に気づかず、不自然な訳文になってしまうこともしばしば…。プロの中でも日本語文章を書くのが上手な人は決して多くありません。しかし、裏を返せば日本語表現力は後天的に伸ばせるスキルです。意識的に鍛えれば誰でも向上できるので、他の翻訳者との差別化を図るためにも、積極的に磨いていきたいですね。
「?」を生まない明快な文章
字幕翻訳では、視聴者が字幕を読む際に頭の中で「?」マークが浮かばないことが極めて大事です。読み手が内容を理解できず戸惑う要因として、字幕に難解な表現や馴染みのない単語が使われていることが挙げられます。例えば、専門的すぎる言葉や一般に浸透していない言い回しは、視聴者の理解に時間を要し、「この単語の意味は何だろう?」と悩ませてしまい、その間にも場面はどんどん進んでいってしまいます。そうした状況を避けるため、文章にはメディアで実際によく使われる表現・言い回し・言葉だけを用いるよう心がけましょう。具体的には、自分が訳出した日本語のフレーズをインターネットで検索し、ニュース記事や番組で使われている言葉か確認します。検索で実例が見つかれば、その表現は視聴者にも馴染みがある可能性が高く、安心して使えます。逆にヒットがほとんどない表現は、字幕に使うと「?」を生む恐れがあります。過去に実績のある言葉遣いを積極的に取り入れ、未知の表現は避けるのが鉄則です。
もう一つ重要なのが、情報を過不足なく「要約する力」です。英語の台詞や文章をただ直訳するのではなく、「つまり、要するに何が言いたいのか?」を素早くつかみ、シンプルな日本語で言い換える訓練が必要です。翻訳者自身が原文の意味や意図をしっかり読み取れなければ、訳文を読む視聴者も理解できません。場合によっては原文に直接は書かれていない背景情報を補足し、文意を明確にすることも求められます。特に字幕は巻き戻して読み直すことができないため、読み手が一度で意味をつかめる表現にすることが大切です。常に「この字幕で本当に伝わるか?」「視聴者が戸惑う箇所はないか?」と自問しながら推敲しましょう。その意識がクセづくと、自分の日本語に違和感を覚えるアンテナが立つようになり、表現の改善点にも気づきやすくなります。
徹底したリサーチとスタイルの統一
翻訳者自身が内容を理解していない箇所は、訳文にも必ず現れます。翻訳作業中に「これはどういうことだろう?」という疑問が浮かんだら、放置せずにリサーチで解消しましょう。背景知識が欠けている状態でそのまま翻訳しても、曖昧な日本語になり、読者も理解に苦しむでしょう。翻訳者に疑問が残ったままでは、当然ながら視聴者にも「?」が浮かんでしまいます。専門用語や文化的文脈など不明点は事前に調べ、腹落ちした上で訳文に反映させることが必須です。
また、複数の情報を同程度に扱う場合はスタイルと言葉のレベルを統一する意識も重要です。列挙する要素同士がアンバランスだと、これも読み手の混乱を招きます。例えば字幕中で「ホースと水」と並べた場合、「ホース」は具体的な器具ですが「水」は飲料水なのか水道水なのか曖昧です。このように種類が異なるものを対等に並べると、「水」という言葉の解釈に迷いが生じスムーズに読めません。「ホースと水道(水)」のように双方を同じ次元に揃えてあげると理解が早まります。同様に、金融会社の広告で「情報と信頼」というフレーズがあったとします。「情報」は会社が提供するものですが「信頼」は顧客が感じるものと性質が異なり、この2つを等しく列挙すると違和感があります。もし訳文でこうした不均衡な組み合わせに出会ったら、言葉の選択や構文を見直しましょう。不要であれば片方を削る、あるいは「豊富な情報提供と揺るぎない信頼関係」など読者が違和感なく受け取れる形に調整することが求められます。スタイルが揃った文章は読みやすく、結果として視聴者の理解スピードを高めます。
さらに、日本語の文法細部にあまりにもこだわり過ぎないことも肝心です。もちろん基本的な文法は守るべきですが、言葉は生き物であり文法規則には例外も多々あります。あまり深入りしすぎると学術的な「言語学」の領域になってしまい、実際の翻訳にはかえって非効率です。大切なのは文法の知識をひけらかすことではなく、読んで伝わる日本語になっているかどうかです。極端な文法議論に陥るよりも、目の前の視聴者にとって自然で分かりやすい表現になっているかを優先しましょう。
知識を広げ取捨選択力を養う
優れた日本語表現力を身につけるには、日頃から知識と思考の引き出しを増やしておくことも必要です。字幕翻訳では常に情報量との戦いがあります。原文の内容すべてを字幕に盛り込むことはできないため、どの情報を残しどれを削るかの判断力が求められます。その判断には世の中一般の知識や常識が大いに関係します。例えば、映画紹介の記事タイトルが「健全な善人が誰一人登場せず『清張の毒』充満!」だった場合、多くの視聴者は「松本清張の作品なんだな」「おそらくハッピーエンドじゃないな」「登場人物は悪人ばかりかもしれないな」といった想像ができるでしょう。この場合、翻訳でも松本清張原作であることを示すのは重要度が高い情報と言えます。一方で細かな設定説明などは省略しても観客は推測できるかもしれません。このように作品や題材に関する一般的な知識を持っているかどうかで、翻訳時の情報選別の精度は大きく変わります。
知識量を増やすには、ニュースや情報番組、話題の作品に日頃から触れることが有効です。それによって「世間の大勢がどう受け止めるか」「何を重要だと感じるか」の感覚を養うことができます。それは翻訳時に伝えるべき内容の優先順位づけに直結します。また、子ども・ペット・命・ジェンダーといったセンシティブなテーマを扱う際には特に注意深い表現選択が必要ですが、これも社会一般の価値観や論調を知っていれば判断を誤りにくくなります。自分の感覚だけに頼らず、世の中の見方とのズレがないかを常にチェックする姿勢が大切です。
情報の取捨選択力を磨く具体的な手順としては、まず原文の各パラグラフ(あるいは一つの字幕分)を読み、そこに含まれる事実・アイデア・比喩などを細分化してリストアップします。そしてそれぞれに重要度の順位をつけましょう。特に比喩表現や象徴的な言い回しは作品テーマに関わる重要情報である場合が多く、優先的に残すべきです。次に、上位の重要情報だけを残し、文字数オーバーにならないよう思い切って情報を削ぎ落とします。大胆に削除した結果、もし字幕の文字数に余裕が出たなら、そのときはじめて二次的な情報を少し戻すことを検討します。この「優先度の高いものを残し、低いものを削る。余裕があれば戻す」という段階的アプローチによって、限られた文字数でも要点が明確に伝わる引き締まった訳文に仕上がります。日本語表現が上手な人ほど手元に情報のストックが多く、必要に応じて取捨選択できる引き出しを持っているものです。逆に表現が拙い人は一つの視点しか持たず、情報の優先順位付けができない傾向があります。常に複数の視点や解釈を想像しながら翻訳に臨むことで、表現の幅が広がり、洗練された日本語訳を生み出せるでしょう。
まとめ:鍛えた日本語力が翻訳の価値を上げる
映像翻訳において、日本語表現力は翻訳者の価値を決定づける重要なスキルです。ただ英語を直訳するのではなく、情報の背景や意図をくみ取り、日本語で再構築する力が求められます。機械翻訳が台頭した今だからこそ、翻訳者には「頭に『?』が浮かばない日本語表現」を作り出す意識と技術が一層求められています。日本語表現力は先天的なセンスではなく、努力で高められるスキルです。日々日本語のブラッシュアップを怠らず、メディアで磨かれた言葉遣いを研究し、読み手に寄り添った訳文を追求しましょう。それこそが英日翻訳者として生き残り、そして選ばれる存在であり続けるために必要なことです。
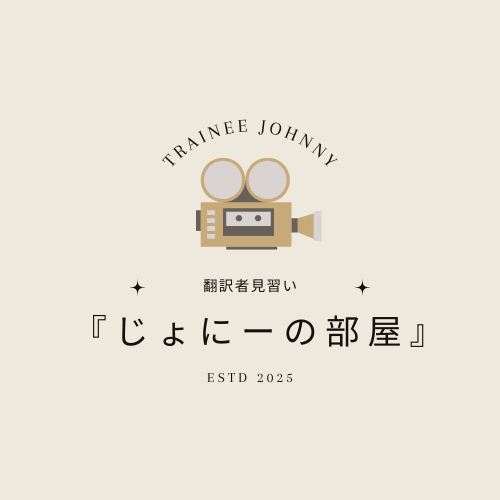
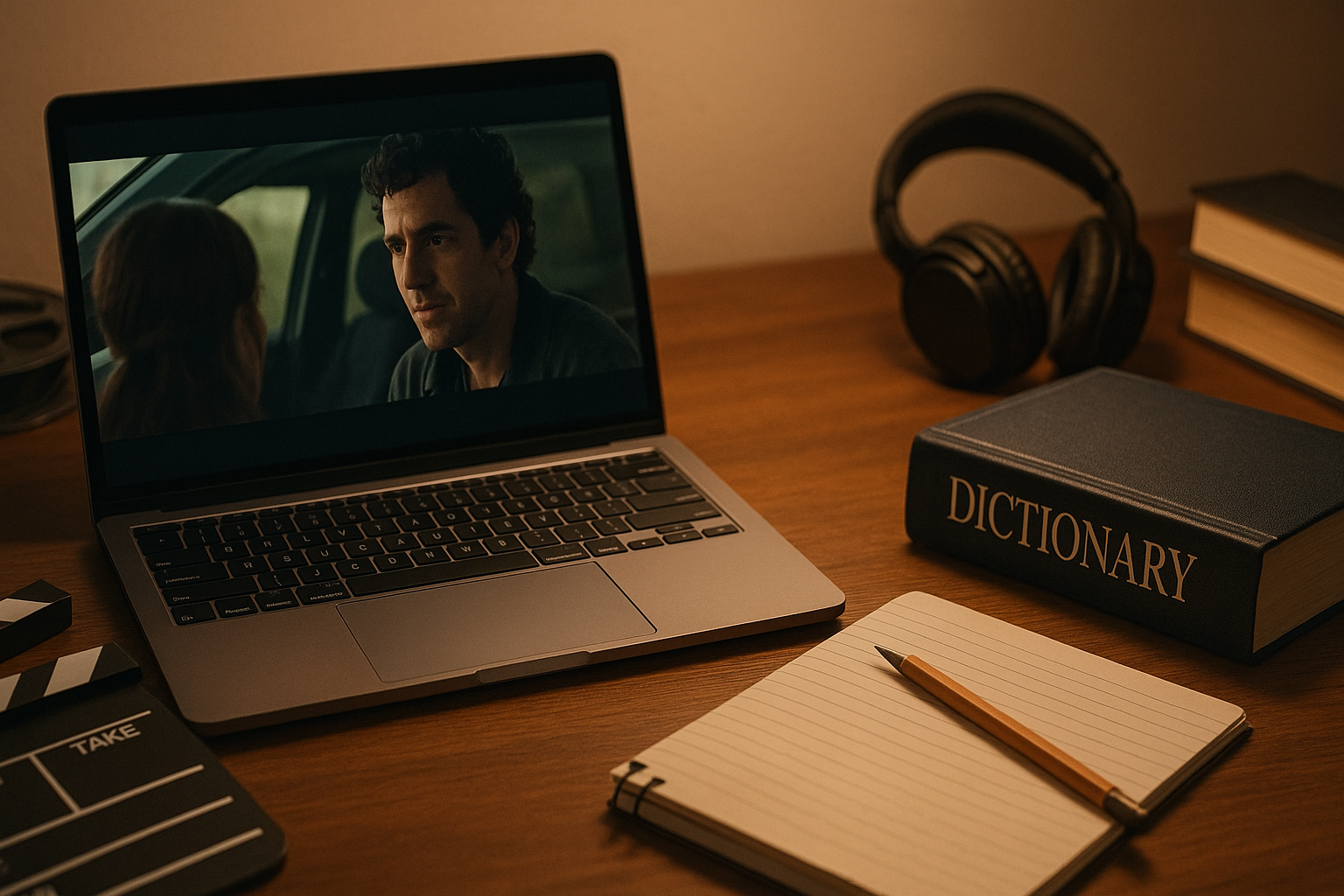
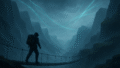

コメント