外国語の映画やドラマを日本語吹替版で見ると、登場人物がまるで日本語を話しているように見えますよね。これは、翻訳者がオリジナルの音声に合わせて日本語のセリフを作成する「リップシンク」という技術によって実現されています。吹替版では原作の音声を完全に消して日本語音声を当てるため、リップシンクがとても重要になります。
この記事では、リップシンク翻訳の基本から吹替と字幕の違いまで、紹介していきます。
吹替翻訳と字幕翻訳の違い
まず、吹替翻訳と字幕翻訳では、翻訳のスタイルや制約が大きく異なります。それぞれの違いを比べてみましょう。
| 項目 | 吹替翻訳 | 字幕翻訳 |
|---|---|---|
| 原作の音声 | 日本語音声に置き換えるので原語音声は消える | 字幕を表示し原語音声はそのまま聞こえる |
| 情報量 | 台詞の内容をほぼそのまま伝えられる | 文字数制限で情報を要約する |
| 視聴者層 | 子供や文字が苦手な人でも理解しやすい | 字幕を読めない人には内容が伝わりにくい |
このように、吹替翻訳では観客が耳で理解するため、聞いて分かりやすい日本語にすることが特に重要です。
リップシンク翻訳の特徴
吹替翻訳には、字幕翻訳とは異なる独特のルールや工夫があります。中でも代表的なのが次の 三大ルール です。
- 尺合わせ: オリジナルのセリフを話している時間(尺)に、日本語セリフの長さを合わせること。
- リップシンク: 俳優の唇の動きに、日本語セリフの発音やタイミングを合わせること。
- ブレス(息継ぎ): 俳優が息継ぎで間を取る箇所では、日本語セリフも同じタイミングで息継ぎの間を入れること。
これらを徹底することで、映像の俳優が本当に日本語を話しているような自然さを生み出せます。逆にリップシンクが不十分だと違和感が出てしまいます。また、字幕では省略されがちな劇中のテレビ音声や周囲の会話も、吹替翻訳では聞こえる音声はすべて翻訳して台本に書き起こします。必要に応じて場面の説明(ト書き)も加え、日本語台本だけで状況が理解できるようにします。
リップシンク翻訳の制作フロー
では、吹替リップシンク翻訳の仕事はどのような流れで進むのでしょうか。一般的な制作フローを簡単に追ってみます。
依頼を受けたら、翻訳者は作品の映像データと原語スクリプトなどの素材を受け取ります。映像とスクリプトを照合して不備がないか確認した上で(素材によっては原語セリフの入っていない音声が提供されることもあります)、映像を見ながら日本語台本の翻訳作業に取りかかります。翻訳したセリフは自分で見直し、必要に応じて演出家やチェッカーのフィードバックを受けて修正します。完成した台本を納品した後、スタジオで声優によるアフレコ(吹替音声の収録)が行われます(翻訳者が収録に立ち会うこともあります)。全セリフを録り終えたら、日本語音声と映像を合わせるダビング(音声仕上げ)の工程を経て吹替版が完成します。
実務上の注意点
リップシンク翻訳を行う上で、押さえておきたいポイントを紹介します。
- 音読で最終調整: 翻訳したら必ず自分で声に出して読み、セリフの長さや息継ぎの位置が合っているか確認します。声に出すことで不自然さに初めて気付くことも多いです。違和感があれば思い切って表現を変えてみましょう。
- 時間と品質の管理: リップシンク翻訳は時間がかかる作業です。プロでも1時間の映像翻訳に1週間要する場合もあります。綿密な調整が必要なので、スケジュールには余裕を持って取り組みましょう。
制作関係者にとって使いやすい台本
吹替版作りには多くの人が関わりますが、誰にとっても使いやすい台本を作ることが翻訳者の役目です。演出家は台本だけで内容が分かること、ミキサーは編集しやすい書式、声優は自然で演じやすいセリフを求めます。
まとめ
リップシンクを駆使した吹替翻訳は、映像に命を吹き込むやりがいのある仕事です。難易度は高いですが、セリフが映像にぴったり合って自然に伝わったときの達成感は格別でしょう。
ぜひ普段から吹替版を観察してセリフの工夫に注目してみてください。短いシーンでも自分で吹替翻訳に挑戦し、声に出してみる練習もおすすめです。地道に練習を重ねて、リップシンクのスキルを一緒に磨いていきましょう!
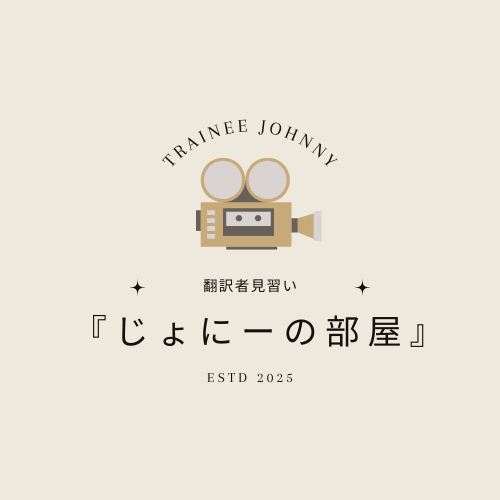

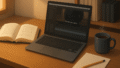

コメント